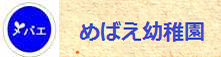第五章 人間学的教育学の確立をめざして
1. 哲学における中心的課題としての人間 <ボルノーの哲学的課題をめぐって>
人間の人間的発達を保障するために、人間の本質についての哲学的探究の成果を、教育学における基本的していくこ課題として提供と、それが哲学における中心的課題の一つである、と言われています。ドイツの哲学者ボルノーが提起している、教育学への提案から学んでみたい。
2. 哲学的人間学 -人間とは何か-
哲学の根本問題は、人間そのそものであります。人間とはどのような存在なのか、という問いにたいする現代の哲学者たちの言葉を聞いてみたいと思います。 “人間は環境世界から自己を解放し、衝動から解放されて、自覚的に対象と関わりうる存在”(シェーラー)であり、“自己自身に対して距離を保ち、客観的に自己自身と関わりをもちうる存在”(ブレスナー)であります。 “人間は本性的に文化的存在であり、動物と比べて欠如存在(生まれつきの武器や保護のための毛皮などが欠けている)であるため、自然が人間に与えなかった武器、装置、衣服、住居、伝統、制度、社会や国家の形態などを、みずから創り出さねばならぬ存在”(ゲーレン)である、と言われます。また、“人間の本質は、あらゆる事柄に対して未決の存在であることであり、世界に向かって開かれた問いとしての存在であると共に、閉じられている存在でもある”(ボルノー)という指摘もあります。 以上のような人間に対する理解に立って、私たちは教育という営みのあり方を考えて いきたいと思います。
3. 教育学的人間学
教育という営みの中にあるあらゆる事柄を、人間存在の全体との関わりの中にひきもどしてきて、教育が人間の生の全体の中で、どのような機能を果たしていくのかを、問うことが教育学の根本問題であります。 人間とは、本質的に学習を必要とし、教育を必要とする存在であります。 人間は“訓練されうる生きもの”(コメニウス)であり、“教育されねばならぬ唯一の生物”(カント)であり、また“教育されるべき、または教育されうる生きもの”(ランゲフェルド)であります。 これまでの教育は、ややもすれば技術論的であり、有機体論的・生物学的な成長に委ねる教育学でありました。その主な特徴としては、連続的・形式主義的・機械論的・画一的な、教育技術に偏った教育学であったと言わざるを得ません。 それは、教育という現象の一部分に過ぎないのです。 元来、人間の本質には失敗とか危機や挫折などといった、成長への妨害や、撹乱(かくらん)というような現象がつきものなのです。そのようなマイナスの要因と深く関わっているのが人間であり、教育を必要とする存在としての人間は、逆にそれらを契機として自己の再生と自己形成を可能にしていくのであります。 子どもを技術的・意図的に操ったリ、生物学的・有機体論的な考え方にたって、連続的・段階的・計画的なプロセスの上を歩かせたりという、一方的な教育方法が巾をきかせ、明治以来のわが国における近代化のためには、それなりに一定の成果をあげてきたのは事実であります。 しかし、これまで見落とされ、あまり取り上げられることがなかった危機や撹乱、妨害などという、予測不可能な出来事が、子どもの発達の過程に存在するという事実を、私たちはしっかりと直視しなければならないと思うのです。こうした現象の中にこそ、人間を人間たらしめていく根本的な契機があるのです。そのような事実を認めることから、これまでの教育全体にたいする見方がすっかり変ってくるという重要な発見があるのです。 私たちは人間学的教育学という視点から、教育のあり方を新しく見直していくことが大切だと思っています。
例えば、ドイツの哲学者ボルノーは、次のように言っています。 “人間は絶えずその意図の新たな方向づけや変更を余儀なくされる。・・教育者は自分の教育計画の奴隷になることを警戒しなくてはならない。” “予見できず、計画出来ない有益な出来事とか、あるいはまた思いもよらない、今までまどろんでいた諸力の突然の目覚めといったことも考えるべきである。” “教育はきわめて限定された範囲でのみ計画可能なのである。” “計画と計画できないものとの交錯するなかで・・教師の・・自由さ・・自由に物事を処理する力”が決定的に重要な課題となってくるのである。<O.F. ボルノー著『問いへの教育』-哲学的人間学の道-川島書店刊より> ボルノーが言っているのは、教育とか指導というのは、予測や予見することの極めて 困難な営みである、ということです。あらかじめ立てた計画通りに指導することは、不 可能なのだというのです。何故なら人間とは、そして子どもとは、抑圧や強制による一 方的な指導によって、深く傷つく存在なのです。
4. 人間学的教育学の課題 <ランゲフェルドの教育思想をめぐって>
M. J. ランゲフェルド著 『教育と人間の省察』 玉大出版部刊より オランダの教育学者、ランゲフェルドが提案している人間的教育学の課題は、次のようなものであります。
(1)子どもの発達を人間学的に捉えること。かれは、機械論的心理学に基づく教育 学の誤りを指摘しています。 例えば、ワトソン(1873-1958)によって提唱された行動主義心理学の誤りや、神経生理学の立場から機械論的神経生理学を批判したシェリントン(1861-1852)の学説の紹介、行動科学的人間工学・自発的動機づけ理論によるティーチングマシン・プログラム教授(スキナー(1904~)への批判、パブロフの条件反射、ヴィゴッキーの強化論、デューイのプラグマティズム教育学等々がもっているさまざまな問題点等を明らかにしています。 現在の教育体系のなかで学習機械化された子どもの姿を指摘しながら、ゲゼルの生物学的心理学に基づくレディネス論や、機械論的条件づけ理論等々が抱えている、非人間的な問題状況を克服していく道を探っていくための、指針が与えられます。
(2)人間としての発達過程における基本的課題を明らかにする
[第一課題]人格的存在としての子ども 人間は自己の内側から、能動的・自己開発的・自己発現的・自己充実的・自己創造的に発達していく主体的・自立的・実存的存在であるという、人間観と子ども観に立つこと。
[第二課題]人格的発達の目的とは何か。 人間は自己の主体者として、人間らしく発達していくことを、本質的に志向する存在であるということが教育の前提であります。故に、教育の目的は人間性の開花であり、発達とは人間らしい成熟した大人になっていく過程のことであります。 人間を自然的・生物学的成長に委ねることは、オオカミ少年の例のごとく、人間には許される事ではありません。また、子どもを勝手気ままな状態で放っておくことも、生物学的・段階的成長に合わせての画一的・一方的な機械論的指導に委ねることも、共に誤りであります。さらに、条件づけ・強化論的発達観に基づく教育方法もまた、子どもの人格的発達との関係の中で厳しく批判、吟味され、人間学的、哲学的教育学の立場から再検討される必要があります。
[第三課題]自己発現や自己実現のもつ人間学的意味 子どもは自然的・生物学的発達の状態から、教育によって歴史的・社会的・文化的な、いわゆる人間的なものに向かって発達していく。その人間的発達を支えている条件は、子どもの自己発現的活動である。 人間は、歴史的・社会的・文化的な様々な営みに積極的に参加していくことで、意味や価値の世界に向かって自己を創造的に実現していく存在なのである。 子どもにとって発達課題とは、常に自己の主体的な課題でなければならない。 子どもの自己発現・自己実現への積極的な意志と意欲が基盤となって、文化創造の営みとしての教育活動・学習活動への参加がなされなければならないのである。
[第四課題]子どもの発達における人間力学的法則について 人間学的教育学の立場から、子どもの人間としての発達、人格の発達を保障していくための時間・空間・人間関係等における人間力学的原則を明らかにしていく必要がある。 子どもの毎日の生活における、時間とエネルギーの関係、個と集団との関係、保育室・園庭・地域・家庭等の環境空間と、それらの環境における教材・教具・遊具などのすべてを子どもの発達との関わりにおいて、問題点を追求し、それらの在るべき姿を明らかにする必要がある。 さらに一つひとつの遊びや活動、日常の学習活動やくり返しの活動についての人間学的哲学的な問いかけと見直しが必要である。
(2)人間学的教育学における発達観と学習との関係
・人格としての子どもと、学習者としての子どもとの内面的・相関的・力学的自己同一性、即ち矛盾の中の自己同一性において生きている子どもを前提とする人間学的発達観に立つこと。
・学習活動における人間学的弁証法の理解から教師の子どもに対する援助が始まる。 客観的事実との対立関係の中で自己を実現し、成長していく人格としての自己と、客観的事実に導かれながら学習していく自己と、両極的自己の間に成立する弁証法的関係の中で、子どもの学習活動は行われる。
・教師と子どもとの人格的出会いからの出発。 子どもがそれぞれ固有の人格として、自分自身になっていくプロセスの中で、子どもを自然的・生物学的必然性(勝手気まま)の過程から、人間的文化的過程への移行を人間学的教育観に基づいて可能にしていく人格的出会いが決定的に重要である。
・人格の発達と教具・教材など道具との人間学的関係についての基本的理解の必要性。 子どもは様々な子どもための文化財との出会いを通して発達していく。 人間の自然的・身体的限界を突破して、歴史的・社会的・文化的領域、すなわち人間的領域を拡大し獲得していくために、人間によって発見され、創造されてきた文化財としての道具(教具・遊具・教材など)との出会いを通して子どもは人間としての発達を実現していく。 本来、道具は手の延長であり、人間による人間らしさの獲得、人格性・主体性の確立と拡大、すなわち創造的な自己実現のためにあるものであり、その逆では絶対にないという認識が基本的に重要である。 5. 子どもの発達と教育方針との関わりについて
<人間学的発達論の確立をめざして>
(1)人間学的発達心理学の課題 ・人間の発達についての二つの側面。
● 自然的・生物学的な動物(生物)としての発達。本能・遺伝的体質や気質に属する発達。
● 教育によって開発され、環境によって変化する発達。文化的・社会的・歴史的な意味と価値の実現に向っていく発達。 この二つの発達側面が、弁証法的に統一されながら、人間は発達していく存在である。 ・人間としての発達。 人間の発達は、文化の伝承と創造という教育的営みの中で行われる。 人間が人間になっていくための、固有の営みの中で、子どもは人間としての発達の過程を歩むのである。 ・人間の発達における文化史的意味 人間は、人類が過去において築きあげてきた歴史的・社会的・文化的遺産の伝承という教育的営みから始めて、人間に固有の有価値的な文化創造・歴史創造の主体者として生きるとき、初めて人間でありうる存在である。 子どもは人類のあらゆる文化遺産に対して開かれている存在であり、同時に現在と未来におけるあらゆる未知なるもの、可能性にすぎないものに向かって開かれている存在である。
(2)ピアジェ理論をめぐって <ピアジェ・インヘルダー著 『創造的知能の開発』 誠文堂新光社刊より>
・構造について 一般的概念規定。一つの全体における諸部分の組み立て。全体と部分とが互いに相関性をもち、有機的に統合されて全体の機能を遂行していくために協働する仕組みが構造である。 構造化とは動的・力学的な概念であり、一つの全体が独自の全体性を失うことなく各部分の調和のとれた特殊化と細分化をすすめていくことである。 固定的な組み立ての概念と共に、力動的な機能概念を合わせもつのが構造である。 中心性と脱中心性とを同時にもつ概念である。 構造とは本来、諸部分の均衡と安定化への傾向と全体的統一への傾向とをもっている。 人間という生命体は、有機的統一の機能をもつ構造を本来的に所有している。各部分は異質性と相反性を保ちながらも、自己調整と均衡を保っている。 構造の本質的機能は、生理的・心理的・精神的に発達のすべての段階において機能する自己調整と均衡である。 この機能は同化によって作動する。 精神的構造は、常に新しい外的な対象を同化することによって変換され、より高次の均衡化に向かう。 ・図式(シェーム)について シェーマとシェーム。前者は図形・図解・構図(単純化)、後者は機能の複雑化ないし複雑多様な応用機能の意味。日常語対学術語。 シェームは哲学的・認識論的な発想の概念。 シェームは対象を認識するとき、ある一つの対象をもっている特殊性を一般性(既知の事柄)に置き換えていくための媒介機能であり、同時に外に向かって反応したり、働きかけたりする時の基盤(精神的な構え)として行動図式というような概念、感性的・経験的・行動的な機能体系である。 シェームが仲立ちとなって、思考と現実認識が結びついていくのである。 ・図式の諸機能
● 意味づけの機能 ―自分にとっての関わりの判断―
● 構造の発達段階にしたがって、感覚・運動的意味づけから抽象的・操作的意味づけに至る無数の段階がある。 感覚・運動的図式、形式的操作の図式など。 構造にも下部と上部の構造があるように、図式にも幾通りもの重層がある。 そこで、習慣図式・知覚図式・直観的図式・象徴的図式等々が発達段階にしたがって複数現れてくることになる。 さらに、具体的操作図式と形式的操作図式との組合せにより無数の図式が現れる。 図式とは具体的対象を処理して構造に組み入れてくる媒介的機能であり、構造に組み入れるとは同化であるから、図式は対象の同化の補助機能である。 同時に、図式は行動と密接な関わりがあり、外界への適応における主導的機能でもある。 生物体の組織の形成過程においては、全体がまず発生し、次第に諸部分に細分化して構造が生まれる。そして、構造の諸要素は相互に独立し、相反的であり、しかも全体を構成するという矛盾の中でそれら諸要素間の融合と調和、相互透入を力動的に関係づけていくのが図式である。かくて、構造と図式とは相関概念であり、同時的に発生し、相補的に発達するのである。
6. 人間発達の構造化をめぐって
(1)教育の構造 ・人間としての発達援助 ・文化の伝承と創造 ・ 社会化による人間化
(2)生活の構造化(三層構造) ・ 基底となる生活 ・ 領域的系統的活動 ・ 中心となる生活と活動
(3)学習の構造 ・目的意識の獲得 ・手段・方法の獲得 ・成就感・成功感の獲得
(4)教材の構造 ・発達のための課題性 子どもの認識と技術とのズレや落差を子どもが発見し、自己の課題として主体的に関わることができるものであること。
・発達の順次性 子どもの近似体験や相似体験、また子どもの発達段階に即応したものであること。
・活動の多様性 発達過程は個々の子どもによって異なる。したがって、活動の多様性を保ち、興味・関心や意欲、技術性や認識の程度において多様性と幅をもつものであること。
7. 教育思想の対立をめぐって
(1)対立の諸相 ・児童観・発達感における対立・・・自然的・生物学的立場と伝統的理想主義 ・教育内容における対立・・・・・
・実学主義・実利主義と古典的人文主義及び発達心理主義と体系的論理主義 ・教育方法における対立・・・・・・
伝達と受容の方法論と自発・能動の方法論 ・学校論における対立・・・・・・・
知識偏重主義と生活・作業主義及び複線型体系主義と統一学校体系主義 ・教育目的における対立・・・・・・
個人的目的主義と社会的・国家的目的主義及び伝統主義と近代主義
(2)教育のあり方についての比較から
人間形成の教育と人間解体の教育。 人格発達の教育と人格疎外の教育。人間への教育と非人間への教育。 自己発現・自己解放の教育と抑制・抑圧の教育。 自立・自律と主体性の確立への教育と命令・指示・禁止による定型化・画一化への教育。 自己選択・自己抑制・自己課題型の教育と押しつけ型ワクハメ教育。 構造的立体的教育と並列的平面的教育等々。
(3)教育における実践的課題についての提案 ・人格発達の条件としての自由について・・・
時間・空間・人間関係における自由、活動における自由、参加と不参加の自由。・意志と感情と価値における自由。・能動・意欲・積極性・自主性・自律性・主体性の確立。経験科学的・実証主義的教育から人間学的人格発達の教育への転換。 ・教育実践の言語化。 実践記録の必要性。 言語による人間行動の諸事実の明確化。 行動の客観的観察と分析による言語化を通して、行動(事実)の意味と価値をアイマイ性から脱皮せしめて明確化していくこと。 言語によって現実を再現化し、深化させていくことにより、分析能力や分析のための視点を獲得していく。より確かに、より深く、より豊かに事実を読み取る力、また言語を選択し決定していく力を獲得していく努力の必要性。
・発達の内容構造
● 精神の発達―予感・直感・洞察・愛・情緒・安定・保護感覚の獲得。
● 身体の発達―身体的自由・労作・生産・意欲・能動性の獲得。
● 認識・知性の発達―言語・体験の経験化、概念の獲得。
● 社会的発達―人間関係・個と集団の育ちの獲得。
● 文化的発達―伝承と創造性の獲得。 以上の5領域における発達とともに、人間は、感覚の発達・意志の発達・感性の発達等を含めて、全人格的・全人間的な発達をとげていく存在である。 ・発達の諸相(アスペクト)
● 知・情・意―精神的・知的発達
● 真善美聖―感覚的・感性的発達
● 身体―生物学的・文化的発達
8. 補助資料
(1)ボルノー(オットー・フリードリッヒ・ボルノー)1903~ 現代ドイツの教育哲学者の第一人者。実存主義哲学(キルケゴール、ハイデッガー、ヤスパース、マルセル、サルトル)を背景とした教育思想を体系的に教育学に組み入れ、近代および現代の哲学思想と対決しつつ哲学的人間学の視点から、広く哲学・教育学・言語学・文学・芸術等の領域における人間の諸現象を通して人間の全体を理解し、また人間の全体からこれら諸現象を理解しようとする課題を、哲学的教育学的人間学の基本的課題としている。 従来の形成ないし成長の教育観を”連続の教育学”と見、”非連続の教育学”を暗示している。 すなわち、人格と人格との教育的出会い(フリットナー)、覚醒(シュプランガー)、人格としての私と汝の出会いと対話(ブーバー)、訴え(ヤスパース)、自己投入(サルトル)等の実存的思考について人間学的、教育学的考察をすすめる中で実存哲学の限界を克服して、人間の本質に根ざした人間学的教育学の確立をめざしている。
(2)ランゲフェルド(マルチヌス・J・ランゲフェルド)1905~ ヨーロッパにおいて、最初に現代的意味において教育的人間学を企画したオランダの教育学者。 発達心理学に基礎をおき、哲学的神学的思索を通して、人間の発達と教育の関係を追及している。 能動的自己形成としての発達(人間は内から形づくられ、人それぞれ自己自身に対する内的関わりをもつ)が、彼の発達論・教育論である。
●ランゲフェルド文献より ”大学の中心はもはや医学部ではない。すでに人間は存在し生きているのだから。これらの人たちをさらに生かし続けることは確かに重要だか、さらに重要なことは、ただ生かしておくのではなく、その生活を人間らしいものにすることである。教育が最も重要な今日における全世界的な問題である・・・大学における一番重要な学部は教育学部である。・・・最も緊急の課題は、この科学や技術を人間の理解と人間の解釈の中に統合することである。” <『教育と人間の省察』(p.192)> 教育の基本的条件について ・ 国家とその統治機構 ・ 子どもの現実 ・ 子どもに対する両親の関係(デューイの『民主主義と教育』・・・家庭・家族・両親の語はない) ・ 自然-人格としての人間の自然。人間を一種の機械仕掛けと見る人間観、機械のことを考える機械という悪夢のような考え方。 ・ 成熟した独自な人格と成るべく、目下成長しつつある子どもという基本認識。<『教育の必要性』 p.67~70> ”教育の人格と学校全体の人格性が極めて重要な意味をもっている。 いかなる学問も、その従属的な位置、すなわち単なる情報の提供という範囲をこえて適用されるなら、学校本来の「人格の形成」という教育的課題に対して致命的打撃を与える以外の何ものでもなくなる。”<『教育における人間関係』p.162> ”教育の中で実に様々な形の「非人間化」の過程が進行しつつあり、教育における真に人間的な関係がいたる所で危機に瀕している” ”人間らしい生が営まれる場としての学校、したがって人生の一局面としての学校をつくりだすのは、教師を中心とする子どもたちの人間的諸関係に他ならない。けれども何といっても根本的に重要なのは、彼らの家庭に対する関係と両親による教育である。”<『教育における人間関係』p.173> ”自己について、それを「刺激・知覚の中枢」と考えたり、他の何らかの機会論的な意味において把握するのでは十分な理解はできない。 人間の自己は複雑な力動的統一(ダイナミズム)である。あらゆる局面における彼の彼自身に対する関係おいて・・仲間たち・・価値の経験・・生活歴・・予想・・生活との取組み‥‥‥あらわになる力動的統一の姿である。自己は、この意味で当の人格のとる位置に関わる相(ポジショナル・アスペクト)である。
――――自己の発達とは、一般に考えられているような単純な意味での「発達」でもなければ、ある固定的な「自己」に達することでもない。 人間は、生物学的なカテゴリーに加えて・・・たえず自分自身の自分で作った条件を創造している。‥‥‥子どもはその身体的な限界を突破していく‥‥‥人間の言葉を発見し、それを使用して‥‥‥人間の歴史や社会や文化の中に入っていく‥‥‥自分の身体を使用し、非身体的な可能性を発見していく過程‥‥‥道具を創り出すといった可能性を発見していく過程‥‥‥が発達である。 発達という語は、あまりにも素朴で範囲が狭い。‥‥‥発見していくという活動を表していない‥‥‥身体はただ大きくなり、より多くの異なったホルモンを分泌するようになるだけでなく、精神に利用されることによって人間の「身体」になっていくということを表していない‥‥‥。”<『自己の発達』p.32>
9. まとめ
現在の人間のおかれている危機的状況から、私たちはどのようにして「人間」をとりもどすことができるのだろうか。 子どもを単なる学習させる機械、条件づけを施されるメカニズムとしてしかみようととしない教育状況を、どのようにして変革していくことができるのだろうか。 人間であることの意味を自ら深く反省し、私たちは人間の教育の本質を見極めていく努力を傾けていきたい。 科学的であろうとして、人間不在の技術主義、さらには単なる方法論や指導の在り方に終始している現状を厳しく批判し、人間観・教育観の問題から教育を見直すこと。さらに科学性そのもの、人文科学・自然科学のかかげる科学性そのものと鋭く対決しながら、科学をこえて科学を支えているもの、言語をこえて言語を支えているもの、人間をこえて人間を人間たらしめているもの、科学と人間の限界を見つめながらその限界の彼方からふたたび人間であることを見つめ、人間であることの意味と価値を吟味し、人間としての栄光、人間でありうること、人間でありえたことを最大の喜びとしてうたいあげていくことの出来るような人間的教育学を確立したい、と願うものである。 私たちがヨーロッパから学びうることは大きい。近代的学問の諸成果はほとんどヨーロッパから移入されてきた。 その科学的実証性、言語による精密な論理構成、事実、あるいは実験により、統計・調査・分析・分類など様々な客観的科学的方法によって理論を裏付け実証していく方法は、まことに優れている。 しかし、言語によって全てを明確にし、透明化しようとする試みには限界がある。ルソーは著書『エミール』の中で、人間には生涯知ろうとしても到底知ることの出来ないものが無数にあることを知ることが真の知識である、という意味のことを言っているが、言語化によって人間が知りうるものは、人間が獲得しうる知識や能力の一定の部分にしか過ぎないのである。人間は言語化しえない部分、それは科学的な統計や調査、分析によっては到底到達することのできない深みや高み、広さにおいて、多くものを獲得しうる存在なのである。 言語とは、本来、対象についての表象作用である。対象について語り、対象について記述するものである。 ○○について知る、というのが言語活動の限界である。人間は、その本質からして、○○について知る前にそのものを・知るのである。しかも、○○について知るとは現象の世界であり、科学の世界であるが、そのものを知るとは直感と洞察、感性や感覚の世界である。 人間は知りえた知識の世界においてよりも、より広く、より深く、より豊かに直感と洞察と感性の世界において生きる存在である。 なぜなら、人間はすでに到りえている段階において完結し、完成した生を生きる存在ではなく、本質的に、より高みにある生、より豊かな、より真実な生を目指して求道的に生きることを運命づけられている存在である。 その時、人間を新たな自己獲得のために動機づけていくものは、言語をこえ、知識をこえた「何ものか」であり、科学的には定義もしくは決定することのできないダイナミカルな衝動である。 直感と洞察によって「獲えた」ものを言語化し、科学性の明るみの中に引きだそうとする試みがその一つであり、さらには直感と洞察のまま、そのものを知るという状態にとどまらざるを得ない知識もある。 例えば、もののあわれ、わび、さびの類いであり、芸術における美の世界であり、人間の出会いにおける感動の世界であり、自然との出会いにおける発見の喜びの世界である。 1981年8月