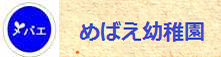第一章 幼児の指導 -その1 原則と展開-
1. はじめに 保育における幼児の指導のあり方やその役割と限界、或いは指導の効果と必要性、および指導における諸条件を、幼児の人間としての全面発達をめざす視点から見つめ直して、望ましい指導とは何かを明らかにし、幼児教育の現場で保育実践に関わっている方々の参考とし、また私たち自身の幼稚園運営についての指針を明確にすることができれば幸いであります。 特に、指導の方法論について、その理念的側面と技術的側面や保育の形態などについて、わが園の保育実践の実態に則して明らかにし、ご批判とご指導を頂きたいと思います。
2. 指導の本質について
(1) 指導の目的とは何か 保育活動における指導の目的を、ひとことで簡潔に表現すれば、「指導のいらない状態」を幼児の生活の中に、実現していくことであります。 教師への依存の状態から抜け出して、幼児一人ひとりがどのように、自分自身の自由と自立を獲得し、生活の主体者となり、幼稚園生活の主人公になっていくか、その道筋を明らかにしていくことが、指導を考える場合の第一の課題であると考えます。
(2)指導の本質とは何か 保育活動における指導の本質とは、いかに「指導らしい指導を行わない指導」を、毎日の園生活のなかに実現していくかという、矛盾にみちた課題であります。 すなわち、幼児にとって指導とは感じられない指導、指導されているという意識を、幼児たちに持たせないような指導こそ、真の指導であると思います。 ”道の道とすべきは常の道に非(あら)ず、名の名とすべきは常の名に非ず”(老子『箴言』1章)という、何ものにも捉われない、融通無碍の多様性・多義性と柔軟性、そして自由性が指導の基本条件であります。 また、指導における教師の言葉かけの問題についていえば、言葉をして言葉たらしめるものは、言葉を越え、言葉を支えている、言葉にはならない、教師の心の深みにある、人間的な共感や洞察、直感に裏づけられている「いわく言い難い、あるもの」によって、幼児と教師の間に、深い共感と同一化の世界を生み出していくために必要なもの、それが言葉であると思います。 その「あるもの」・・「人間的なるもの」「見えない実体」「心の深みに沈潜しているもの」とは、教師の心の奥深くに潜む「人間存在に対する畏敬の念」とも言うべきものではないでしょうか。 人間の教育とは、様々な欠陥をもつ不完全な人間によって、教育されなければならないという、永遠に解決されることのない、矛盾と限界のなかで行われる営みであります。そして人間の限界を超えるところから、祈りともいえるような思いによって、大いなるものの力に委ねることしかできない営み、それが人間の教育であり、指導なのではないでしょうか。 そのような考え方に立って、望ましい指導のあり方とは何か、を明らかにしていくことが、幼児教育の現場にある私たちにとって、最も大きな課題のひとつであると考えます。
(3)指導における「指導意識」と「支配意識」の問題 「指導なき指導」という矛盾に満ちた、困難な課題に向かっていくとき、真っ先に取り除くべきものとして、教師の指導意識と支配意識とがあげられます。 よく言われることですが、「教室王国」の支配者・権力者として、子どもの上に君臨するような教師のあり方を、徹底的に排除し、否定することから、真の指導への道が開かれてくるのだと、私たちは確信しています。 「指導してやらなければ」、「教えてやらなければ」という発想を、徹底的に排除し、転換していくところから、指導の本当のあり方が見えてくるのであります。 過去、約150年におよぶ、近代の学校教育における、教師中心主義の「授業」という観念を根底から捨て去り、子どもが人間として全面的な発達をとげるために、絶対に不可欠な条件として、「自己教育を促す教育」すなわち「指導なき指導による指導」という、逆説的な基本原則を確立することが、教育に関わる者にとって、緊急の課題であると考えます。 黒板を背にして、一方的に知識や技能を子どもに「注入」し、「与えて」きた、古典的指導法を支えている伝統的な教育観を否定することであります。 即ち、子どもを知識や技能を一方的に注入される「いれもの」とみる、機械的、非人間的子ども観の否定であり、放っておけば子どもは何もしないし、何も覚えようとしない怠け者になる、という古来からの伝統的子ども観を否定することから始めるのす。
(4)学習における二重構造について 学習する子どもの内面には、「教えられる者としての子ども」と、自分自身の力で育っていく「学習の主体者としての子ども」という二つの側面があります。 教育という営みには、教師から子どもへの、人類が営々として築いてきた、子どもが人間として育ち発達していくために必要な、さまざまな文化遺産の伝達という第一の側面と共に、教師の指導や助言・援助を伴いながら、子ども自身が自らの内面的な促しによって揺り動かされ、子どもの時代にしか生み出すことのできない、子ども独自の文化を主体的に創造していくという、第二の側面が厳然として存在するという、学習活動における二重構造乃至指導の重層構造についての理解が、決定的に重要であります。 保育者は、ややもすると外面的・形式的な第一の側面である、文化の伝達についての指導を優先させて、第二の、より本質的な子ども自身による育ちや、子どものもつ創造的な側面を見逃しがちであります。 しかし、子どもの主体性や自主性を無視した一方的な指導が、一般的に言って依存型・受け身タイプで、命令服従型・指示待ち型の無気力・無感動・無意欲の「三無主義」の子どもを作り上げていることは、周知の事実ではないでしょうか。 子どもが充分な意欲を持ち、自らの知的好奇心に燃えて、能動的・積極的に自らの課題に挑戦し、主体的な喜びに満ちて、さまざまな困難を乗り越え、さらに次々と新しい、さらに困難な課題を自ら発見して、とりくんで行くような、生き生きとした創造的な状況を実現していくためには、学習における第二の構造に着目した指導を、展開しなければならないのは、当然であると思うのです。
3. 指導の方法と形態
(1)指導における諸原則について
●子どもの自主的な活動に任せる。自主性の原則。 園生活における、最初の第一歩の大切さと重要さを、教師が深く、徹底的に理解することから、子どもたちの幸せに満ちた、しかも本当に充実した生活が始まることになります。 子どもの「いたい所にいる自由」「行きたい所に行く自由」「やる自由とやらない自由」を保障することによって、子どもの「地金」というか 、本来のその子自身が等身大の姿で現れてくることが、その子の園生活の第一歩で無ければなりません。その子の、その子自身による育ちと発達は、実にその子の地金を出し切った、その所からしか、始まらないのであります。このことはどれ程強調しても、し足りない大切な原則の一つなのです。 園生活のスタートのところで、つまずいてしまったら、そのロスは実に大きいのです。 ある園の実例を紹介しましょう。その園では入園後の1,2週間、子どもたちを保育室に入れて、鍵をかけてしまいます。鍵のかからない部分は、ガムテープで「目張り」をして、子どもたちが安定するのを「待つ」のです。 「お母さんがいい!!」「お家へかえりたい!!」と泣き叫ぶ声が、次々に伝染して保育室の中は、ものすごい泣き声の坩堝(るつぼ)となります。しかし、子どもたちは、1,2週間すると、うそのように静かになり、泣くのをやめて、新しい環境に慣れてしまう、ということです。 一体、子どもたちは、そこで何を学ぶのでしょうか。まず第一に「いくら泣いていても事態は解決しない」ということです。子どもたちは、泣くのをやめることによって、環境に順応したことを周囲の大人に示し、部屋の外に出る自由を獲得することを学びます。幼稚園という所は、「いろいろなきまりごと」があって、それらのルールに従わなければ、快適な生活はできない、ということを園生活の最初に「学習させられる」のです。 環境(園や教師)が要求するルールに従うこと、それらを素直に受け入れることから、園生活が始まるのです。子どもは、当然のこととして、自分の思いや願い、要求などを自分のなかに「押し込め」て、自分勝手なことをしない、人に迷惑になることをしない、自分のわがままを押し通そうとしない、とても「良い子」の仮面をかぶって園生活をスタートすることになります。 そして、ついぞ「本当の自分を出さなくなる」のです。子どもの「地金」は隠れたままで、抑圧された形のまま幼児期を過ごすことになってしまいかねないのです。 そして、親や教師の指示や命令に、よく従う子どもが育つことになり、そうした指示や命令・合図がなければ、自分からは行動を起こせない、受身の子ども、指示待ちの子どもが育つことになったりするのです。
●自分の人生を生きる。自己決定の原則 私たちは、そのような保育を、この50年間否定し続けてきました。今もそれは正しいと確信しています。他人の指示や命令によって動かされる生活は、人間的ではないのです。そうではなくて、私たちは子どもに自分の人生を歩んでもらいたい。他人まかせの、或いは他人からの借り物の人生を歩んではならないのです。 自分の足で立ち、自分の頭で考え、自分の意思で選び、自分の心で決定し、自分の力で取り組んだり試してみて、自分なりにやったことの責任を取るという、主体的な人生を生きてもらいたいのです。 だから、幼くとも、「三つ子の魂百まで」といわれる通り、一人ひとりの子どもたちが、自分らしい、自分でなければ生きられない、その子だけに固有の「生きざま」を、幼児期にこそ、自分の手でしっかりとつかみ取ってもらいたいのです。 めばえ幼稚園の入園直後の園庭には、保育室に入らない子が泣きながら立っていたり、どこかにしゃがみ込んだりしている姿があります。しかし、やがてそれらの子たちは、自分の意志と自分の足で、自分の保育室に入っていくようになり、自分の遊びの生活を始めていくのです。 その、自分の足で踏み出していく第一歩の尊さと大事さは、何ものにも代えがたいものなのです。その子の人生における、最初の自分自身による決断によって踏み出される第一歩だからです。 私たちはその子の手をとり足をとって、むりやりにその子を保育室まで運んでしまう、というような「力による解決」を選びません。それはその子にとって屈辱の体験に違いないと思うからです。 その子の自由な意思による「体の移動」を大切にすることに、「こだわる」からです。
●自分の世界をつかむ。自由の原則 子どもがじっくりと、十分な時間をかけて、自分の好きな遊びに取り組むなかで、自分自身を見つめ、自分自身を発見し、自分のテリトリーを広げ、自分の世界を深めていく自由を、最大限に保障することが大切であると確信しているからです。 子どもとは、怠け者などではなくて、本質的に好奇心の極めて旺盛な存在であります。 3歳児などが良い例であり、少し幼稚園に慣れて、安定してくると、園の中を隅から隅まで探検し、探索し始めます。どこに何があるか、だれがどんなことをしているか、この先には何があるか、と彼らの好奇心はとどまることがありません。楽しいことがあれば、夢中になって熱中します。我を忘れ、時間を忘れて無我夢中になって集中するのです。それが子どもの本来の姿だと思います。
●夢中になる。夢中体験の原則 子どもは、そのようにして自分の世界をつかみ、広げていくのです。 これは、人間にしか与えられていない、特別の能力であり、動物は決して夢中になりません。動物が夢中になって我を忘れたときは、天敵に襲われて自分の命を失うとき、それが動物の生きる世界であります。 人間だけが、数十万年の進化の末に、夢中になれる能力を身につけたといわれます。未知の世界に自分を投げ出していく勇気と決断は、人間だけができることなのです。 そこには、時間を忘れ自分を忘れても、絶対に安心であるという無意識の意識が人間を支えています。世界と人間に対する基本的信頼感覚であります。この感覚に助けられて、子どもは見事に夢中になるのです。その夢中体験のなかで、子どもは自分をつかみ、自分を発見し、自分に自信をもつように育っていくのです。今、そのような体験の乏しいまま、幼児期を通りすごしてしまう子どもたちが、あまりにも多いことを考えると、わが国の将来が大変心配になります。 ●子どもの園生活における自分だけの時間を保障する。時間保障の原則 ゆったりとした時間・じっくりと自分の遊びに取りくむ時間・自分を忘れて没頭し、無我夢中になれる熱中体験をもつ時間等々を充分に保障することが大切です。子どもが自分で育とうとする意思を持っていること、また子どものなかに潜んでいる、潜在的な自ら育とうとする意思が、必ずおもてに現れてくることを信じて「待つ」余裕を持つことが大切なのです。
●子どもの園生活にける自分体験を保障する。感動体験の原則 自分で考えたり、自分で選んだり、自分で決めたり、自分で試したり、という自己選択と自己決定の原則によって、自分自身の生活の基盤を、自分で獲得していくことを、十分に保障していく幼稚園生活が、決定的に大事だと思います。 例えば子どもの「地面体験の自由」ということを考えてみましょう。 子どもはいつも地面や床に近い生活をしています。すぐに地面や床にぺたりと座り込んで遊ぶのが、子どもの自然の姿です。汚れるとか、きたないとかという感覚は、子どもにとって不自然なのです。 汚れることを嫌い、土や泥にまみれることを、嫌がる子どもが増える傾向は、随分以前から見られますが、その主な原因は親の育児態度によるものであり、幼児期に十分な遊び体験を、経験しないまま親になってしまったため、子どもに自由な遊びを、保障することができない親が増えているという、悪循環現象が起こっているのではないでしょうか。 それは、子どもにとって大変な危機であり、子どもは日々の生活の中で、楽しさにあふれ、喜びに満ちたさまざまな、感動的な場面体験や躍動的体験を、ついぞ経験しないままに、乳幼児期を通過して、幼稚園に就園してくることになり、上記のような神経症的、病的なまでに、汚れることを嫌う子どもが、育ってしまうことにつながるのです。 そのような子どもも含めて、夢中になって遊んだり、活動する楽しさを経験しながら、充実感・躍動感・達成感・成就感をたっぷり味わう生活を通して、子どもは見事に変容していきます。 遊びのなかで、さまざまな思考錯誤体験や危機体験・挫折体験等々を含んだ、問題解決学習を積み上げながら、自らの力で克服したことを、実感できるような感動体験に満ちた生活を、充分に保障することが大切なのです。
●信頼感の原則 子どもは乳幼児期に、安定した自己概念をしっかり獲得することができるためには、十分に愛され保護されて育つことが、何よりも大切であります。そして、自分の生まれてきた世界と、共に生きる人間(親・教師や仲間たち)に対する確かな信頼感と愛情、そして「私は愛され受け入れられている」という、確かな受容感覚を獲得することが必要なのです。さらに周囲の大人や仲間たちとの信頼関係に支えられて、自分自身にたいする信頼と自信、自分を愛する心、仲間たちや大人たちを愛情やおもいやりをもって受け入れていく心が育つのです。愛されることなく育った人間は、愛することのできない大人になるという、恐ろしい循環が一方にあることを忘れてはならないのです。
●画一的指導否定の原則 教師の画一的・機械的・形式的・固定的・一方的・強制的な、押しつけやえさやり的な、やらせの指導を徹底的に否定することが大切です。「やらせればできる」とか「鉄は熱いうちにたたけ」とかという、早期教育や天才教育のような、子どもの心や願いを無視した、一方的な指導は、子どもを殺してしまいます。
●教師の位置と役割。子どもの人格尊重の原則 子どもの目の高さで、子どもの内面に寄り添い、できることから子どもに任せ、教師は子どもの協力者・仲間・援助者となり、本質的には子どもに「仕えるもの」として、子どもの横または後ろに立つという、自分の位置と役割を外れないことが重要です。育とうとする子どもの芽を、摘みとるような残酷な指導を否定して、子どもを一人の人格として見、扱う教師であることが、なによりも大切なのです。
●参考文献[1] <ティヤール・ド・シャルダン著 『自然の中の人間の位置』 春秋社刊>より、 20世紀における最大の預言者的学者と呼ばれた、北京原人の発見者シャルダンは、現代における人間の課題を鋭く提案しています。 ”模索は、まさに解放という臨界点に達した人間エネルギーがとる、自然な本質だからである” (p.111) “人間の自由エネルギーの解放、そしてまた模索の抬頭など・・結局、何かを見出そうと身構えている人類にほかならないのではないだろうか。”(p.114) 子どもの遊びには、非常に多くの「模倣」と「模索」からスタートするものがあります。お家ごっこ、お母さんごっこ、お店ごっこ、などをはじめとして、子どもが戸外にでて自分の体を使って、いろいろな運動遊びをしていくときにも、年長の子どもたちのしていることを「模倣」して、自分なりの身体活動を試みるところから、始まることが多いのです。「模倣」して、何かの動きをする、ということは、まさにそのことをしたいという、子どもの内面の願いが、形をとって外に出てくることです。自分を表現したいという要求が、具体的な行動となるのです。 自分を解放して、思う存分エネルギーを発散させようとしている、子どもの願いが「模倣」行動のなかにあるのです。新しい可能性に向かって自分を解放していく営みが「模倣」なのです。やがて、子どもは「模倣」を突き抜けて、新しい自分だけの世界を切り開いていきます。それが文化の創造なのです。
参考文献[2] <E.H.エリクソン著 『幼児期と社会「」 みすず書房刊> より、 現代アメリカの最大の発達心理学者エリクソンは、子どもの発達を阻害する要因について、深い洞察に満ちた警告をしています。 “外部からの統制は・・子どもの心に怒りと不安の循環を生じやすい。・・他人から操られたり強制されたりすることは、とても耐えられないという心のしこりが、不耐性としていつまでも残ることになる。”(p.189) ”子どもの遊びは、自分の身体をおもちゃにして遊ぶことから始まり、自分の身体を中心にして展開する。これを、自己宇宙の遊戯とよぶ・・”(p.282) ”自発的な遊びの中にみられる自己治療的傾向・・勿論、無意識的にしかも自動的に起こるのであるが・・自我の力を決して過小評価してはならないのである。・・幼い子どもの自我であっても・・”(p.298) 「よく遊ぶ子はよく眠る」とか「よく眠る子はよく育つ」という、昔の人の言葉があります。十分に遊びの生活をもっている子どもは、情緒も安定しています。遊びに熱中していくなかで起こるいざこざやぶつかり合いなども、心の傷になったりはしないで、楽しい思い出に転化させてしまうのです。自分で自分の傷を癒していく力をもっているのです。宇宙の中心としての自分という存在に、安心してしかも自信を持って住んでいる子どもは、とてもおおらかで、子どもらしい子ども、生き生きとした子どもです。 反対に、いつも大人からの指示や命令によって動かされている子どもや、自由な遊び行動を制限されている子どもは、とても不安定な心をもっていて、いらいらして怒りやすかったり、反抗的だったり、動きがとても鈍かったりする子どもになってしまいます。エリクソンの指摘は恐ろしいほど本当のことなのです。
(2)指導の具体的展開について考える その一 遊びや活動への導入について
● 子どもの興味・関心からの出発 子どもは自分自身の興味・関心に揺り動かされて、さまざまな遊びや活動に、取り組んでいく生活のなかで、自己動機づけの習慣を獲得していきます。そのためには、自由な一人遊びを、ふんだんに体験していくことが、極めて大切なのです。 自由な遊びのなかで、楽しさ・喜び・充実感を思う充分に味わえるような園生活の流れが、毎日の幼稚園生活に必要なのです。 そして、子どもが取り組んでいる、遊びや活動のもつ意味や価値を、教師は子どもの発達に応じて、折々に子どもに理解できる言葉で伝えることによって、子どもに自分の遊びや活動について、自己評価ができるようになっていくのを、日常的に援助するのです。そのような指導の積み上げによって、子どもの自己動機づけの習慣を強化していくこと、それが指導における言葉かけという営みのもつ大切な機能のひとつなのです。
教師は子どもを励ましたり、子どもの楽しさに共感したり、やり過ぎず少な過ぎない、適時適所の程よい援助を与えることにより、遊びや活動への意欲を盛り上げていく努力を惜しんではならないのです。また、援助の必要な時と所についての、細やかなそして鋭敏なセンスとタイミング感覚を、日常の保育のなかで磨き上げていかなければならないのです また、日常の生活の中で、時には子どもに他の子どもたちの遊びや活動を見させたり、観察させたりして、他の子の遊びの内容や楽しさ等を伝えたり気づかせたりすることも大事です。そうした「遊びの一般化」というか、さまざまな遊びへの目的意識を育てることや、遊びをはやらせ、さらに遊びの深まりを援助し、遊びの巾を広げたり、遊びの質を高めていくための、教師の日常的な、そしてさりげない小さな努力の積み重ねが、子どもの生活をさらに豊かにしていくために、重要な指導のポイントとなることは言うまでもありません。 子どもの心によびかけて、遊びへの意識を強めたり、意欲を引き出したり、遊びへの目的意識を抱くように仕向けていくために、他の子たちによる楽しい遊びの世界を「見せて」、子どもを楽しい遊びの世界へと「よびだし」ていくと共に、子どもの心に「ゆさぶり」をかけていくことが、指導の大切なポイントの一つであります。 子どもが「わたしもあんなことやりたい」という、目的意識と意欲をかき立てていき、子どもの興味・関心を豊かに引き出していくような、環境づくりと体制づくりが決定的に大切なのです。
●好奇心・探求心への訴えと課題への気づかせ 子どもの遊びや活動を、日常的に深く見つめていくなかで、その子の「今」の課題を引き出していき、気づかせていくことが大切です。また、自分の「できること」「やれること」に対して、「やりたい」「やってみたい」という目的意識を抱いていくように援助したり、子どもがやったこと、できたことに対して、心からの賞賛や励ましの言葉を与えることによって、子どもの達成感や成就感を豊かに増幅させていくのです。「楽しかったね、またやろうね」という充実感にあふれた子どもの言葉が、毎日聞こえるような園生活が大事なのです。 子どもが自分で取り組んでいる、遊びや活動の意味や価値に気づいていくことを、日常的に援助していくことです。子どもは教師の共感的な言葉や態度を通して、自分の遊びの楽しさや充実感を、自分の中で確かめていくのです。未分化から分化への援助は、教師にとって日常的な営みであります。未分化的・直観的理解、感覚的知覚として、「何となく分かっている」「何となく感じている」という段階から、具体的な場面での「あっ、そうか体験」による気づきや発見を通して、子どもの抱いているイメージの明確化を進め、より確かな理解や了解の段階へと、子どもが成長し発達していくのを援助していくのです。 また、感性的・感覚的な理解から悟性的理解・分析的理解へ、さらに理性的理解・理性的認識にいたるプロセスを、好奇心や探究心に導かれながら、ゆったりと確実に、子どもが歩むことのできるように、具体的な場面において援助していくことが大切なのです。 学習の主体である子どもの内面で、時間をかけて選択したり批判したり分析したりしながら、蓄積されていく知識や情報によって、自分の判断や認識(感覚的・直観的理解を含む)を質的に変化させながら、自分を再発見し再認識していく学習体験(遊び体験)を、毎日の園生活のなかで、豊かに経験していけるような、幼稚園生活の基本的な体制をしっかり確保することが、幼稚園と教師に与えられている課題なのです。 その二 発展と展開について
●一人遊びの充実から仲間づくりへ 子ども同士が具体的な遊びや諸活動を通して、ごく自然に仲間としてつながっていく、ゆったりとした仲間づくりのプロセスを、暖かく見つめ余裕を持って援助していくことが大切です。 子どもが対立・葛藤(けんか・ぶつかり合い・やったりやられたり)等による、子ども同士の自己主張のぶつかり合いを通して、次第に問題発見の力や問題解決の方法などを獲得し、協調と協力の芽が育つ段階へと、一人ひとりの子ども自身が自分の発達課題を、しっかり踏みしめていくプロセスを大切にしたいと思います。 子どもたちが共に育っていく関係は、その前段階における「やったりやられたり」する関係から出発して、次第に成り立っていくことを、特に最近の若い父母に認識してもらう努力を大切にしたいのです。子ども時代をいわゆる「良い子」で過ごしてきた親の場合、そして外遊びや仲間遊びをあまり知らないで、子ども時代を過ごした親は、「けんか」の体験をもたないケースが多いのです。「藪のかげからわが子をのぞく」という昔の諺にあるような、わが子と客観的な距離をとって、対応することのできない親が、増えている時代であります。 子どもたちが、仲間との人間関係を築いていくための、基本的な場である遊びの生活を、徹底的に大切にし、時間的・空間的・物的なあらゆる条件を、整えていくことを大切にしたいのです。自分の遊びをしっかりと持っている子ども、自分の大切にしたいことを一杯持っている子どもは、自分のなかに「譲れないもの」をもつ子どもでもあります。だから当然のこととして、時に対立し争うこともあって当然なのです。自分の願いを実現しようとして、子どもはけんかをします。そして自分と同じ願いをもっている他者に出会うのです。 そのようなぶつかりあいやけんかを通して、相手を理解し、譲り合い、協力することや赦すこと、相手を受け入れること、また程ほどの手加減等を体で学習していくのです。 かつて、めばえ幼稚園の保育を見学にこられた、多くの幼児教育関係者たちが驚かれたことの一つに、めばえの子たちが激しい取っ組み合いのけんかを、本気でやっていることであります。桐朋幼稚園の大場牧夫先生(故人)や学習院幼稚園の先生方始め、多くの方々が、子どもの違いに驚いておられましたが、それは子どもが違うのではなく、子どもの生活がちがうからだと、私は思っています。
●身体自我の確立をめざして 自分の身体を自由に動かし、思う存分に活動することに伴う、子どもたちの開放感や充実感、そして「楽しかった!! もっとやりたい、またやろうね!!」という、喜びと感動体験の積み上げを通して、子どもが自分自身の身体自我を確立していく生活を大切にしたいと思います。 この時期の身体的運動的な、活動の質と量が豊かに保障されていることが、幼児期の感覚運動的認識段階の内容を決定し、その後の科学的・知的認識段階への発達の土台を形成すると言われています。 感覚と認識の発達との相互関係は、子どもが自己課題にひらかれ、主体的に「自分のこと」として、園生活や家庭生活に立ち向かっていく、具体的な多くの実例を通して確かめることができます。 例えば、運動会の「リレー競技」を成立させるプロセスで、様々な試行錯誤体験を通して、ルールを発見・定着・伝達しあう、という子どもたちの姿を通して、身体自我の確立に伴う充実感や感動の体験が、いかに深く子どもの認識や社会性の発達に関わっているかを知ることができます。(現代と保育第五号・全園で取り組む遊びと保育・参照)
●課題性と可能性の相互関係(教材による援助) 指導なき指導とは、子どもの自己教育力の形成に関わる逆説的原理であります。 ”発達の段階に適合した指導こそが、発達を有効にするという逆説に似た結果を生む”(勝田 守一著『教育と認識』国土新書 p.54)といわれるように、子どもの発達の可能性を蓄積していくためには、できる限り多くの豊かな自己課題に取り組む体験を、子どもに保障していく毎日の生活が必要条件であります。 そのための教材選択と、きめの細かい教材の系統化を、教師の一方的な押し付けによる「教える論理」からではなく「子どもの主体的な生活と活動の論理」(遊びの論理)から組み立てていき、豊かな課題性をもつ遊びや活動を、園生活における全てのプロセスのなかに実現していくことが、保育における最も大きな課題の一つであります。(場面の構成・後述) 単なる物やことにすぎない、さまざまな素材を、子どもの発達に有効なものとして、教材化していく課題も日常的に大切なことです。単なるものやことに過ぎない素材を、いかに豊かな課題を持つ教材に変えていくか、という課題であります。そこには教師の鋭い観察力と洞察力が必要であります。子どもの遊びや活動を深く見つめながら、子どもと教材との関わりのなかで、何がどのように子どもを変え、子どもの発達のために役に立つのかを見極めていく力、気づいていく感性を、教師は日々の実践のなかで磨き上げていくものでなければなりません。 また、教師相互の伝え合い、育てあい、磨きあう連帯関係が、決定的に大切な条件であります。互いに相互の実践を厳しく見つめあい、より優れた保育実践を生み出すために、日々の子どもとのやりとりを深くみつめあい、語り合う関係が大切なのです. 教師の仕事には、教材による子どもの発達援助という、極めて重要な一面があります。
●緊張関係と定着 -教師の価値観について- 指導性の問題として、教師のもつ価値観やクラスづくりにおける価値基準は、子どもの個と集団の発達にとって、きわめて重要な意味をもっています。 言いかえれば、教師と子どもの間の緊張関係に関する事柄であります。発達に適合するとは、単に子どもにおもねたり、甘やかすことではありません。 教師は個々の子どもの、その時々における発達の状況に合わせて、より「固い食物」「より厳しい現実」を与え、より「抵抗感のある活動や教材」を用意していくことによって、困難や行き詰まりの状況を子どもの生活のなかにつくりだし、子どもに「迫り」「要求」していく形での、厳しい援助を選択することが、具体的な園生活のなかで、日常的に行われます。教師の価値観と価値基準によって、人間として生きていくことの厳しさを子どもに要求していくのです。そのような緊張感と抵抗感をもつ「場」が、子どもの生活をつくり生みだしていく「生活の場」としての園生活なのです。 子どもとともに生みだし、創り上げていく保育乃至生活とは、教師も子どもも共に人間であることが前提となり、より人間にふさわしいあり方を追及していく厳しさを内包している営みを通して、子どもの生活の中に実を結んでいき、より困難な自己課題に挑戦していく、子どもを育てていく生活なのです。 子どもだましの、偽物やまがいもので済ませてはならないのです。例えば私たちは、子どもたちが木工製作に取組む場合、絶対に子ども用のちゃちな道具は使いません。れっきとした大人用の、大工道具を使うのです。それが子どもを大切にすることなのです。
その三 仲間づくり -集団化について-
●早すぎる集団化をさけること 仲間との生活を生み出していくプロセスを、子どもの必然性に任せ、大人の論理を押しつけないことが大切です。子どもが幼稚園に入園して、真っ先に感じることは、一体何でしょうか。恐らく、それまでの家庭生活と違って、あまりにも多くの子どもたちがいることに、大きな戸惑いや恐れ、プレッシャーを受けることと思います。そして自分よりも一才乃至二才年上の子どもに対して、とても大きな威圧感を感じることでしょう。 「お友だちと仲良くしましょう」とか「一緒に遊びましょう」とかと声をかける前に、子どもは自分の居場所を見つけ、自分が安定できることが、何よりも必要なことだと思うのです。入園したばかりの子どもは、自分のことで精一杯なのです。 そうした子どもの心に寄り添うなら、幼稚園の4月、5月は一人遊びの充実や自分の生活の安定、別の言葉でいえば個の安定と確立が、何よりも大事なことであり、園生活における最初にして最大の課題なのです。 自分の生活とその内容(遊び・仕事・活動)を、押しつけや借り物ではなく、しっかりと自分自身のものにしていく子どもが育つことこそ、何よりも大切なこの時期の生活と保育の課題なのですから、無理に友だちを押しつけたり、仲間遊びを要求したりせず、一人でいること、一人でしたいことを十分に保障することが大切なのです。 まして、子どもが安定するようにという名目のもとに、「あなたのお友だちは、この人よ」などという押しつけは、望ましい指導とは言えないのです。
●対応遊びへの発展 自分の要求をもつ子どもが、他の子どもと関わることをごく自然に求めていくようになっていくプロセスを、教師はのんびりと、しかし細心の配慮をもって待ち、見守るのです。 子どもは園生活に慣れて安定してくると、当然のこととして友だちを求めて、一対一の対応遊びや、一緒に座って食事をする友だちを見つけて行動するようになります。 なんとなく「うまが合う」というか、「自分のフィーリングにあう」友だちを、子どもは自分の意志や好みによって「選ぶ」のです。 園生活における、子どもの自己選択の自由と権利を大事にする、という基本的な姿勢はどんなに小さなことの中にも、常に貫かれていなければならないのです。
●小集団・グループづくり 入園当初、単なる「群れ」であり「烏合の衆」であった子どもたちは、やがて一緒に何かをする仲間を見つけてつながっていきます。 同じことをして遊ぶという、共通の目的をもつ仲間や仲良しの友だち、そして生活の中であれこれのことを一緒にやろうとする、共通の思いや願いによってつながる生活集団・仲良しの仲間グループが生まれてきます。 さらにこの「目的的集団」が、その集団の中の様々な問題を自主的に解決したり、一人ひとりが自分の役割を分担しあったりする機能を発揮していくようになり、「機能をもつ集団」に発展していくのです。 いわゆる「小集団」(小さなグループ)による遊びや活動が、子どもの成長と発達に大変有効な役割をもつことになってくる段階です。小さなグループの多様な活動のなかで、子どもは実に様々なことを学習していくことになります。 子どもが仲間の中で「いもこじ」のようにもまれながら、社会化していくプロセスがいよいよ始まるのです。 教師は、子どもたちに園生活の中での、いろいろな場面や活動に対応していくために、必要となるグループを作っていくことを提案していくことができるようになります。 例えば、芋掘りに行くとき、グループで一緒に行動しよう。畑についたら脱いだ靴やお弁当、リュックなどを同じところに置いておこう。そして掘った芋をグループごとに集めようなどと呼びかけて、グループの名前や目印になるものを作ろう。そのために自分の好きな友だちとグループになろう、と提案したりします。そのような教師の提案に動機つけられて、子どもたちが自分の好きな友だちを選んでいくのですが、そのプロセスのなかで、誰がどの子と仲良しであるか、この子とあの子はうまくつながらないとかという、子ども同士の関係が見えてくることになります。
●集団活動のダイナミズム 年長5才期の後半になると、小集団の活動はいわば成熟期を迎えていきます。 小集団による自主的な活動を軸にしながら、集団同士の関係も見えるようになり、クラス単位の中集団による自主的な活動や、クラス運営なども相当程度可能になってきます。 長期にわたる見通しをもち、集団のダイナミズムとでもいうべき力動感と躍動感にあふれる集団的活動が可能になります。そして園全体の大きな集団での行事活動などについて、ある程度の長期の見通しをもって取り組んだり、計画的に日程を立てて、行事に必要なものを製作したり、自分たちで自主的に運営にあたって行くようになるのです。 この時期になると、子どもは自分自身のやりたいことと、クラスの活動に必要なこととを、見事に仕分けをして生活できるように成長してきます。いわば、個人の課題と集団の課題とを主体的に統一して捉えていき、自分のしたい遊びとクラスやグループとしての活動の時間配分などを、自主的に決めてたりして、正に園生活の主人公にふさわしい生活を展開していくのです。
●集団思考について ”一人一人の子どもたちが、主体的に参加することで発展する、集団的な思考の流れ”(勝田 守一著『教育と認識』国土新書 p.110)としての集団思考のもつ教育的意味と価値を最大限に評価したいと思います。 教師や大人たちからの指示や命令を、ただ受け入れるだけの受身的な生活態度を徹底的に否定して、自分たちの言葉で考え、自分たちの目で本質を見つめ、自分たちの責任において、やりたいことややるべきことを、その場その場の状況にふさわしく選びとっていく子どもたち、そして仲間との集団的な思考の流れを生みだし、一人ひとりが自主的に活動に取り組んでいく子どもたちを育てていくためには、そのような子どもが育つことのできる生活の土壌が大切であります。 子どもたちは、日常の生活の中で、小さな自分の願いや思いを教師の援助によって実現していく経験を、2年ないし3年の園生活を通して、山のように体験してきます。子どもたちの中に蓄積され醸成されてきた、そのような成就体験が、園生活の最終段階での集団活動のなかで「炸裂し」「発酵し」てくる形で現れるのであります。 子どもは自分の発想と仲間の発想をぶつけ合い、統一し、練り上げていくプロセスのなかで、時には激しく対立したり、けんかまでやって一致点を見出したり、譲り合ったりして、みんなのものやクラスの活動に必要なもの等の製作活動を展開していきます。集団思考の坩堝のような状況のなかから、これが幼児の作品なのかと、驚くようなものを子どもは創造していくのです。
(3)指導形態についての原則
●十把ひとからげの機械的・形式的・一方的な、指示や命令による指導形態は最低最悪の子ども殺しの指導であり、人格否定と人間否定の指導法であることを確認したい。
●遊びとは、やりたい人が、やりたいことを、やりたい時に、やりたいだけやる、という原則に最大の特徴があります。それに反して仕事とは、やるべきことを、やるべき人が、やるべき時間に、最後まで責任を持ってやる、という原則をもっています。途中で止めてはいけないのが仕事であり、遊びはいつ止めても差し支えないものなのです。やらなくてもいいのが遊びです。 私たちは、幼稚園におけるどのような遊びも、そして仕事も(子どもにとって仕事も遊びなのですから)、やりたい子から始めるという、遊びの原則を貫くことを大切にしています。そして「やりたくない」という不参加の自由をいつも認めることにしています。その子の「今」やりたいことを否定しないこと。今やりたいことを持っている子に、無理に別のことを強要しないこと等の諸原則を守ることが、結果として自主的・主体的な子どもを育てるための、もっとも確かな道であることを約半世紀の保育実践を通して確かめてきました。
●「○○したいもの、よっといで」という遊びへの呼びかけから始まる、子どもの世界における伝承遊びの原則を貫くこと。 子どもの自主的、主体的な好奇心・探求心・探索意欲・興味・関心に依拠する指導に徹することによって、子どもは自分の責任において行動するという、人生に対する基本的態度を身につけていくのです。
●やらない子ややりたくない子、「そのこと」に意欲をもたない子への「ゆさぶり」や「よびだし」は、楽しさいっぱいの充実感に溢れる遊びや活動を、その子の目の前で展開することによって、ごく自然に行われるのです。
●やった子・分かった子・できた子から、まだやらない子・やれない子・やろうとしない子へのよびかけや伝え合いは、ごく自然に行われ、伝えあい教えあう子ども同士の連帯関係が育っていくのを援助していくのです。
●誰が始めたのか分からないけれど、夢中になって取り組める活動・楽しいから参加する活動・いつの間にか結果として子どもたちが意欲と目的意識をもって参加してくる活動を、日常の生活のなかに、ふんだんに組織していくのが教師の一番大切な仕事のひとつなのです。 ●子どもの心が、教師・仲間・環境にむかって豊かに開かれ、同時に身体も解放されて、「どこでも・いつでも・誰とでも」、それが楽しくて充実感のある活動や遊びなら「何でも・やりたいだけやれる」ような、本当の自由に貫かれている生活体制を、子どもが心底から確信できるような指導を、実現していくことを心がけたいものです。
●指導の形態は、指導の理念から必然をもって生まれ、現われてくるものであります。教師の人間観・子ども観・教育観そして指導観を土台として、創造的な姿をもって見えてくるものであり、いわば日常的な園生活の姿そのものと言っても過言ではないのです。
●子どもの試行錯誤体験・挫折体験・行き詰まり体験・葛藤体験・修羅場体験などを、豊かに保障していく指導の在り方を追求していくことが必要です。 子どもに任せ、子どもが解決し、子どもが克服していく過程を見守り、支え、必要最小限の援助にとどめる指導のなかで、子どもが自ら育っていく生活を保障することを第一としたいものであります。
●教師が余計なことを言ったりしたりしないためには、教材の選択と分析を前提とした、充分な予測と見通しをもつことが必要であり、教師集団の育ちが何よりも大切な条件であります。 子どもが、どこで、どんな風に行き詰まり・挫折・間違い・課題の発見や解決等々の体験をしていくかを、十二分に見通して活動形態や指導のあり方を選択していくことが重要な条件となります。
4. 指導なき指導 -子どもの自己教育を促す指導-
(1)自己による自己の教育 指導とは、本来、指導する者が指導される者に意識され、見えてしまった時には指導とはいえないのでありまして、「指をさして、導く」と書く通り、指をさしている本人が見えているだけでは、どこへ導くのか、その指さす方向が確定しないことになります。指導者の指さすその先に目をやることによって、初めて指導の実があがるのです。子どもが自分の目で目標を見出し、自分の意志で歩き出すところから、自己による自己の教育が始まるということをわすれてはなりません。教師が中心となって、あれこれの指示をして、子どもを引きずりまわすような指導は、本当の指導ではないのです。
(2) 人間の教育とは、人間をして人間たらしめていく営みであり、いわゆる植物栽培型・動物飼育型・木工製作型等の非人間的方法は断固として退けなければならないのです。 条件付けや強化論的な機械的方法を厳しく吟味し、否定すべき部分を明確にして、排除していくことが必要であります。鉢物の植木の手入れをするような植物栽培型の指導とは、自分の好みや思いどおりに枝を切ったり、曲げたりして、木を整えていく方法であって、教師の思いや要求どおりに子どもを育てようとする古典的指導法であります。また動物飼育型指導とは、教師の一方的な餌やり式の指導であり、木工製作型とは、既定の設計図どおりに物を組み立てていく方法であり、指導計画どおりの指導、本時中心主義というか、あらかじめ決めたプランどおりに、同じものを同じだけ、全ての子どもに体験させたり、学習させる方法としては大変優れていますが、一人ひとりの個性や願いを無視して、一方的に効率よく一定の知識や技能を詰め込むために編み出された、非人間的指導であり、明治以来日本の教育界に君臨してきた、教師中心主義の「やらせ」指導であります。そうではなくて、子どもの自発活動を基盤とした、「自己による自己の教育」を可能にしていく指導のあり方を、日々の園生活の具体的場面において探求し、吟味していく営みがなければ、教育はその本来の目的を果たすことはできません。人間は動物でも植物でも木工製作物でもないのです。人間は尊厳に満ちた人格的存在として、教育されなければならないのです。
参考文献[3] <E.H.エリクソン著 『幼児期と社会。』 みすず書房刊>
”幼児は生存に対する基本的な信仰・・永遠の宝物・・が自分の態度の180度の転向によって、すなわち、自由に選び強制的に専有し、頑固に排除したいという厳しい願望が突如として起こることによって、危険にさらされることはない。
”(p.323) ”自発性はすべての行為にとって無くてはならない部分であり、人は何を学ぶにしても、また何をするにしても、果実の収穫のような単純な労働から企業組織に至るまで、自発性の感覚を必要とする。
”(p.328) ”子どもの超自我は原始的で、残忍で、かつ妥協を知らない。・・・子どもが自己抹殺ともいえるほどの激しさで自己を抑制し、制限する事実・深刻な退行や執拗な恨みを発達させる事実・・・人生における最も深刻な葛藤の一つ・・親に対する憎しみ”(p.330) ”子どもは物を共同で作ることに熱心であり、またそれができる。構成したり、計画したりする目的で他の子どもたちと合同することを好み、またそれができる。そして教師たちから喜んで学ぼうとし、理想の手本を進んで模倣する努力をする。・・・可能なことや実体的なものへ目を向けさせ、幼児期の夢が活動的な大人の生活目標に結びつくことを可能にする。
”(p.332) (3)モデリング(見本)による指導 子どもの自己同一化への要求、即ち自分自身でありたいという基本的要求の充足から出発して、子どもはもっと大きくなりたい、強くなりたいとか、○○ができるようになりたい等々、より拡大され充実した自分を目指そうとする要求をもつようになります。いわゆる成長への願いと欲求を強くもつようになるのです。2才から3才にかけて、何でも自分でやろうとして、手出しや手助けされるのを拒否する傾向や、やろうとしてできないと地団太踏んで悔しがったりするのは、より大きくなりたいという欲求の現れであります。 子どもは新しい自己に向かって、自己を突破していこうとする意志を、持ち始めているのです。そのような成長への意欲や要求を子どものなかに呼び出していくために、「モデリング」による間接指導は、幼児期において最も有効な指導方法の一つであるといえます。
(4)教師によるモデリング -伝承と創造-
伝承遊びをはじめ、数多くの子どものための遊びや、文学、音楽、造形活動等々の文化材にふれる体験を始め、基本的な生活態度の育成というか、生きる姿勢の形成にかかわる体験、或いは空想の世界のなかで、物語の主人公になりきって、自分の感情を対象のなかに移入していく体験等々の、幼児期に経験させたい様々な諸体験は、もっぱら教師を仲立ちとして子どもの生活のなかに実現していきます。自由を真に保障されて、園生活を送っている子どもは教師を信頼し、その指導や提案そして教師の教育的要求を喜んで受け入れてくれるように育ちます。子どもは教師によるモデリングを通して、子ども文化や人間としての基礎基本となるものを伝承され、それらを足場として自分たちの新しい子ども文化を創造していくのです。
(5)子ども同士のモデリング作用は園の基本的生活体制から生まれる 子ども同士で育てあい、鍛えあう、集団のダイナミズムが発揮される「場」、また1対1の個別的な関係においても、きめ細かな「伝え合い」や「刺激の与え合い」が展開される「場」が、子ども同士のモデリング機能の発揮される場面であります。 年長児の豊かな遊びの場面は、そのまま年中少児に対する「楽しさへの呼び出し」であり、まだ十分に自己発揮できないでいる、年中少児に対する「ゆさぶり」でもあります。 この「よびだし」と「ゆさぶり」こそ、年長児の年中少児に対するモデリング作用でありまして、「あんなことをやってみたい、できるようになりたい」、という目的意識をもつようになる場が、子どもの遊びの場面なのです。 さらに、日常の小さな生活場面において、教師の予想をはるかに越える、数えきれない程の年長児のモデリング作用が働いているのが、幼稚園という場の特徴であります。それは、ひとえに園の基本的生活体制のあり方にかかっていると言えます。 すなわち、「開かれた園・開かれたクラス・開かれた教師・開かれた子ども」という基本的体制の確立が第一の条件であり、閉ざされ固定化した、形式的な「わがクラス中心主義」の体制からは、絶対に生まれてこないのであります。 子どもを教師の支配のもとにおかず、子どもの自発活動・興味・関心に基づく主体的活動を全面的に支持していくと共に、園全体の子どもたちを「わがクラス」の子どもとして受容し保育していく、ティーム・ティーチングの基本姿勢が必要であります。 他クラスの子どもが、自分のクラスの活動に大きな影響や貢献をしてくれる等々の出来事が、日常的に起こるような、自由でのびやかな雰囲気が、園を豊かに包んでいることが大切であります。
5. 子どもの自由と自己教育
(1)人間の人格発達と自由 人格の主体者としての自我意識を獲得していくために、人間は自分自身の固有の存在感を幼いときに獲得しておくことが、その後の性格形成に極めて大きな影響を及ぼすといわれています。 「自分自身であること」「自分が、今、ここに、立つ」という存在感を実感できる生活体験の質と量を、どれほど豊かに子ども自身のものにしていくかが、保育における人間学的課題であります。 他人(親や教師を含め)の指示や命令・合図によって動かされ、やらされている生活体制に慣らされてしまうと、子どもの諸感覚器官はすべて受動的・依存的な志向性によって支配されることとなり、自己主張や自己選択力を欠いた性格を形成することになります。私たちは身体自我の確立から、責任的自我に向かっていく、子どもの発達の過程をこよなく大切なものとします。 「目玉保育」とか「お土産保育」とかといわれる、親をくすぐって喜ばせるような、一方的な教え込みによる、「指導の皮をかぶった非指導」が、子どもの人間性を破壊してしまう危険を、はらんでいることに着目する必要があります。 人間は、身体の自由(行きたい所に行く・いたい所にいる・やりたい事ができる)、心の自由(意志・願いを実現する)、感情の自由(喜びや感動を表現する・じっくり味わう)、考え行動する自由(考えた道筋にしたがって試行する・行動を選択し決定する)等々を、充分に保障された生活を通して、望ましい人間的な発達を遂げていくことの出来る存在であることを再度確認したいと思います。
参考文献[4] <エドワード・ホール著 『かくれた次元』 みすず書房刊>より。
”かごに入れた動物は鈍感になりやすい”(p.231) ”我々は、ともすれば人間の人間たるところが、彼の動物的本性に根差していることを、忘れがちである。”(p.7) ”どの動物もそれなしでは生存ができない、最小限の空間を要求する。この空間がその動物の臨界空間である。・・・臨界空間が手に入らなくなったとき「臨界状況」が生じる。
”(p.26)(犯罪・暴力少年の背景)
(2)自己の確立とは 自己を自覚する「場」或いは体験とはどのよなものなのでしょうか。 自分は周囲から充分に理解され、受け入れられ、愛されている、という安心感が子どもの安定した「自己概念」を作り出し、それを基盤として自信に満ちた自己主張をするようになっていきます。たとえ、一時的なわがままやかんしゃくを起こして、周囲の大人たちを困らせても、発達の為の一里塚として、寛大な対応をしてくれる大人の存在を通して、子どもは「赦し」とは何か、「受容」とは何かを学んでいくのです。 そして、大人の目や評価を気にしないで、豊かな自己主張のできる生活を通して、子どもは自己をあるがままに受け入れる、自己受容感覚を獲得していくことになります。 おどおどしたり、大人の目や態度を気にする子どもや、大人の気に入るような振る舞い方を身につけている子どもの場合、他者による受容体験を欠いていたり、人間や世界に対する信頼感や人格的・人間的な相互愛情関係が、十分に育っていないことがあります。 自分が選択し決定する行為や言葉が、周りの大人や仲間に受け入れられているという、受容と信頼の相互関係は、子どもの人格および性格形成の基本的条件の一つなのです。 そのような生活基盤と生活体制の上に、子どもの自己獲得と自己拡大を支える保育が生みだされ、成り立っていくのです。 自己発現から自己開放へ、さらに自己実現への道を、子どもはもっぱら自己課題に、主体的に挑戦していく日々の生活の中で体得していきます。 子どもの自己確認と自己確立のひそやかな、そして厳粛なプロセスの中に、私たち大人は軽々しく、土足で踏み込むような、心ないことをしてはならないのです。 子どもが自分の存在の確かさと、かけがえのない、そして尊厳に満ちた唯一の人格としての、人間存在への気づきをつかみとって、自己を確立していく過程を、私たちは子どもの傍らに寄り添いながら、受容と信頼のまなざしを注ぎながら、少しでも援助できるように、畏敬の思いと祈りをもって子どもを見守るのであります。
(3)「成熟してくるもの」を待つ 個々の子どもの中に、また集団としての子どもたちの志向性の中に、徐々に積みあがり、盛り上って、やがて成熟してくる、生き生きとした気分や意欲の高まりを、教師がじっくりと待つことがとても大切なのです。 子どもの思いや願いは、すこしずつ深まり、高まっていくものなのです。例えば子どもの遊びを観察していて気づくことは、遊びと言うものは、はじめから威勢良く「火」がつくものではなくて、一定の時間の経過や、活動の積み上げがあって、だんだん楽しさが増してきて、参加している子どもたちが生き生きとしてくるのにつれて、活発になり、やがて爆発的な沸騰点に到達し、集団のダイナミズムとでも言うべき、猛烈なエネルギーを発揮するようになっていくものなのです。 その緩やかな経過を無視したり、無用な手出しや余計な口出しをすると、子どもはそうした大人の干渉によって、熱が冷めてしまったり、時に依存的・受動的、時には反抗的にさえなって、自分自身の主体的な興味や意欲を、失ってしまうことになります。 日常の保育実践の中に、そのような誤った指導が行われていないか、教師集団による厳しい吟味が、日常的に必要なのです。 私たちは、子どもの生活や活動のなかに、成熟してくるものをじっくりと待つ姿勢を、教師がしっかり持っていることが、とても大切であるということを、沢山の事例から学んだのです。
(4)一つの実例を思い出します。 今から40年ほど前のことです。私たちの園はキリスト教による情操教育を、保育の大切な柱としてきましたので、その頃、毎朝決められた時間になると、朝のお集まりとなり、集会と礼拝を行うのが慣例でありました。 そして朝の体操のレコードが流れると、子どもたちはどこにいても、その場で「はとぽっぽ体操」を始めたものでした。 その頃、注意深く子どもたちの動きを見ていると、朝の集まりの時間が近づくにつれ、それとなく遊びの場から離れて、片付けの作業から逃げる子たちがいるのに気づきました。 「おれ、遊んでなかったもん」と言って、片付けという面倒なことから逃れてしまう子どもに、腹を立てたものです。 さらにひどいことは、集まりの時間になると「お集まりだぞー!」と叫んで、それまで何人もの子どもたちが、時間をかけ手間をかけて、高く積み上げて楽しく遊んでいた砂山などを、どーんと足蹴にし、壊して走り去る子どもの姿でした。 まるで、もっと遊びたいのに、もうやめる時間だ、という怒りと悔しさをその砂山にぶつけているように思われたのです。 私たちは時間をかけて話し合い、朝の集会と礼拝を止めることにしました。遊びへの要求が満たされず、欲求不満のままで参加させるような、形だけの礼拝や集会には意味が無い、という結論でした。 もっと思う存分に子どもの遊びの時間を保障したいということになったのです。 そして驚いたことには、子どもの目つき、顔つきが変わってきたこと、子どもの遊びが変化したことでした。遊びが大きくなり、そして深くなったのです。子ども同士の関係も目立って緊密になり、園生活が活気に満ちたものに変わってきたのです。 そして、子どもたちの生活の流れにそって、それぞれのクラスごとに、その日の子どもたちの遊びの生活のなかで、最も適当な時間を選んで行われる集会や礼拝も、以前と違い落ち着いた静かな雰囲気のなかで行われるようになったのです。それ以来、私たちの園では合図のレコードを使いません。音や合図などによって子どもの動きを誘導するような、条件付けのために音や音楽を利用しないのです。さらに運動会も卒園式も、幼稚園のあらゆる行事についてリハーサルや練習なしのぶっつけ本番が当たり前のことになりました。
6. 場面体験について
(1)「場面」の構成について
●「場」とは 「場」とはトポス(トピック、ユートピア等)・プレィス・場所・間であり、上下・左右・前後の区別をもつ「自然的な場所」と「物を内につつみこむ場所」という二つの性格をもっています。 中村雄一郎は『術語集』(岩波書店)の中で、場所の四つの側面をあげています。 象徴的なものとしての場所・身体的なものとしての場所・問題の具体的な思考や議論に関わるものとしての場所・根拠的なものとしての場所(共通感覚論より)という四つであります。 彼は、「間」としての場所を、それは存在自体ではなく存在同士の隙間として、空白でありながら、かえって存在を活気づける働きをもっている、と示唆に富む指摘をしています。 デカルトは「場所」という空間について、”縦・横・高さの拡がりをもつこと”という、均質空間・抽象空間の考え方から自由になる必要を指摘しました。 「場」とは、何よりも人間の意識的自我と精神の土台であり、そこにおいて人間存在が生きて、立ち続ける基底としての場であります。
●「面」とは 面とは、顔面・表面・おもて・仮面・ペルソナ(人格)の現れとしての「面」であり、「相」(位相)、姿、形としての面であります。 面とは、人格であり人間の自己自身の中核であります。 ”われ思う、故にわれ在り”(デカルト)、”汝自身を知れ”(ソクラテス)といわれた、「知」の根源としての自我ないし自己でもあります。 近代的「知」は自我の確立から始まり、現代の機械的・合理的な科学の知を生みだし、人間をも機械の一部に組み込むに至りました。 しかし今や、人間の回復と復権を求める時代、ポスト・モダンの時代に入り人間の本質が問い直されています。 自我とは、単なる主体ではなく、他者とは、単なる対象ではないといわれます。 自己の内なる第二の自己、自己に対立するもう一つの自己(ワロン)、主客同一の未分化の自己を捉えなおすところから、人間をもう一度獲得することが現代の課題であります。
●「場面」とは 場面とは、人間以外の動物には絶対に経験することのできない、極めて人間的・人格的な出会いを体験する場であります。 「場面」を経験することは、人間にとって認識を組織化し体系だてていくために、欠くことのできない条件であります。 動物の体験は、常に条件づけであり、そこから学習されるのは反射行動のみであって、系統的・体系的な知の領域を構築することはできません。 「場面体験」とは、「そこ」に向かって自己を投げ出し、自己を危機にさらしていく場の体験であります。 人間とは、つねに自己がこれまで経験したことのない、新しい場面に向かって、自己の立っている基底から離れ、自己を破ってそこへ出ていこうとする存在なのです。 そのような自己突破の体験が、自己の底を破って行われるときに、人間は自己の立つ場を自ら放棄し、新しい自己の基盤を「場面」体験を通して獲得していくのです。 人間の創造的な行為の場が、そこに現れてくるのです。 人間の主体的自我とは、常にそのような自己投棄ないし自己放棄や自己突破を通して、新しく獲得され、拡大していくのであり、そのような営みによってだけ常に生命的かつ創造的でありうるのです。 二つの自我の「間」(はざま)において、矛盾と苦しみを担い、常に悩める自己である人間は、自己の底を破り自己から外へ出ていくことによって、逆に新しい自己に到達する、という逆説の中に生きているのです。 この自己の「生きる場」としての自分自身とは、さらに「大いなる場」において「生かされている」自分でもあります。 その「大いなる場」が「世界」であります。 コスモス(世界)とは、自己が生きる場であるとともに、生かされている場であり、同時に、世界とは実に自己自身でもあります。 「生きられる世界」としての自己(ミクロコスモス)と「生かされている世界」としての宇宙(マクロコスモス)とは、主客同一の世界であります。 人間は自己の存在の底を破り、自己を支えている無限の世界に出ていくことで、二元論の世界からの自由を獲得します。 「能」における、形なき形、心身合一(身体と精神との合一の世界)の世界は、厳しい修業によって会得されるといわれますが、保育に携わる教師にとって、場面の構成ないし構築の仕事もまた、厳しい試練と修練の場といえるのであります。 (2)場面の理解と場面づくりの方法
●場面を今として捉えること 子どもの生きている場、活動し流動し躍動している場、現在としての「今」を徹底的に充実して生きようとしている場、同時に過去の一切を「今」において統合しつつ、新しい未来を形成しようとしている者の、活動の場として場面を捉え、日々の保育活動のなかで、どのような場面体験を、子どもに提案し経験させるかを、適時適所に決断し、選択していく営みが保育者の仕事であります。 参考文献[5] <メルロ・ポンティ著 『行動の構造』 みすず書房刊> ”有機体は、自己に対する事物の作用を自分で測定し、そして物理的世界には類のない循環的過程によって、自己の環境を自分で限界づける”(p.222)
●場面を構成する素材は生活のすべてである 自然体験・地面体験・時間と空間体験・人間体験・動物や事物体験・様々な遊びや製作活動・仕事・行事・遠足・散歩・集会等、生活のすべての内容や出来事が、場面を構成する素材であり、場面体験のための教材なのです。 単なる「もの」や「こと」にすぎないそれらの多様な素材を、子どもがそれらに関わることを通して、子どもの発達の為の貴重な教材に変え、生かしいく生活を、子ども自身の主体的な選択に委ねることが決定的に重要であります。 子どもが選択し自己決定していく、場面体験の量と質が、感覚諸器官への入力を決定し、感覚・感情・情緒の発達、運動諸機能の発達、特に人間として根源的能力である、共通感覚・全身感覚・生活神経等の発達、即ち人間としての全面発達に大きく影響していくことを念頭におき、場面体験の量と質を問いつづけることを大切にしたいと思います。 豊かな、そして多様で自由な場面体験の保障された環境での、日々の生活を通して、子どもは「僕もあんな事してみたい」「私もあんな風になりたい」という、成長への自然な同一化への要求とあこがれや願いを、自分自身に向かって抱くように育っていくのです。
<倉橋惣三の誘導保育 ”さながらの世界””生活を、生活で、生活へ”参照> 参考文献[6] <ミンコフスキー著 『生きられる時間』 みすず書房刊より> ”生命的躍動・創造的躍動の軸を形成するものとして・・目的に向かって全存在をあげて赴く・・人格的躍動・・本質的・根源的・・常に生き生きと未来を創造し続ける”(p.55~56) ”我々の内には、生き、かつ行為したいという、ただ一つの根源的欲望しかない・・”(p.62) (3)場面体験と時間体験
●場面体験とは時間と空間における人間的体験であり、時間や空間との関わり方、関係のあり方を学習する場であのます。 教育とは、子どもを自分がもっている時間との、正しい関係へと導いていく営みです。 時間の量的な経過による、子どもの発達との関係を研究したり、過ぎ去った客観的な時間の量を測定したり、時間の流れの中での自分の場所や位置を、見つけたりする能力を育てる研究などではなく、時間に対する正しい内面的な関係を確立していくことが、教育における本来の課題であります。
●時間とは 時間とは消えていくもの、失われるものであります。 有限な時間の中で生きるという、はかない存在としての人間、そして 自分に気づくこと、気づかせていくことが、指導の大きな課題の一つです。 人間とは本来空しいものであること、生命とは本当にもろいもの、弱いものであること、壊れやすく、よるべない存在としての自分に気づくこと、さらに孤独とか寂しさとか、人間の本質についての様々な体験は、子どもの日常生活、特に遊びの中で、また動物の飼育活動や植物を育てる活動等々において、ふんだんに体験されることです。 遊びの崩壊の体験や一人ぼっちの体験等、子どもの園生活の中には人間として味わうべき全ての要素があります。 根本的な事実は、人間とは「死」に向かって生きている、ということであります。 死とは一切が無くなることである、という体験学習も園生活のなかで、折々に起こることであります。 時間への教育という課題は、避けてとおれないものとして、厳粛に受け止めなければならない、人間の教育における重要な課題の一つであります。
●自由と時間との関係について 時間をもつということは、時間に対する自由があることです。 大事なことに集中し熱中する能力と、非本質的なことを無視する能力、ないし態度を学習することが必要であります。自分の時間を自由に、主体的に生きるという基本的な態度を身につけることが、幼児期における教育においても、重視されなければならないのです。
●時間を守るとは 時間とは流れであり、自分の行動を時間に合わせたり、決められた時間を守ったりすることで、生活のリズムが成り立っていきます。 ぐずぐずする・焦る・早すぎる・遅すぎる・急ぎすぎる等々の体験は誰にでもあるが、時間を機械的・固定的・形式的・非人間的なものにしないためには、時間に対する人間的・主体的な態度を育てる必要があるのです。 常に余裕をもって、時間をおしんだり、浪費することなく、時には忍耐をもって、その事に最も適した時間を、勇気と決断によって、用いていく落ち着きの態度が必要であります。 そのためには「間」の感覚、いわゆるタイミング感覚を育てることが大切であります。 自己決定の瞬間的な処理能力、決断する力を身につけるために、自分の時間を最も適切な瞬間に用いる態度を育てることが、教育における大切な課題の一つであります。
(4)時間の種類
●人間の生活は時間の流れの中で営まれる。 昼の時間、夜の時間、遊びや仕事、勉強の時間、暇つぶしや自由な時間、個人的時間、社会的共同の時間、物事に集中する時間とぼけーっとしている時間、緊張と弛緩の時間、春・夏・秋・冬等の季節によって異なる生活時間の変化、そして生と死の時間・・等々、人間にはじつに様々な時間の持ち方と過ごし方が、可能であります。 子どもは幼児期の生活のなかで、そうした様々な質と量のちがう時間への対応の仕方を学習することによって、将来の人間的成熟への準備をしていくのです。
●時間の構造 時間には「体験される時間」と「計測される時間」との二つの構造があります。 人間にとって意味と価値をもつのは前者であり、一つ一つの体験される時間には、それぞれに質の差があります。 早い時間と遅い時間、目が回るような忙しい時間と、のろのろと終わりのないような時間、退屈で死にそうな時間と楽しい充実した時間等々、子どもは実に沢山の時間体験を生活のなかで自分のものにしていくのです。 喜びと悲しみとは、全く別の時間意識の中で成立します。喜びは、まさに喜んでいる現在の時間体験であり、悲しみは過ぎ去った不幸や痛みの経験への振り返りの時間体験であります。 これは自己充実と自己喪失ないし自己解体という、二つの方向への自己体験と結びついている時間体験の構造であります。幼児期の子どもにとって望ましいのは、豊かな自己充実体験の蓄積であって、自己否定や自己喪失体験でないのは言うまでもないことです。
●遊びと無為の時間について 暇な時間とは、自分自身に帰る時間・自分の好き勝手な時間・無為の時間・何もしない時間・ぼけーっとしている時間、等々を学習するための時間であります。 自分だけのひみつの場所、私的な空間と時間をもつことの人間的な意味や、遊びなど活動性に満ちた時間体験のもつ意味と価値を明確にしていく必要があります。と同時に、無為の時間のもつ人間的な意味や価値についても、正しく評価しておきたいものです。
●時間を越える体験をもつ子ども 時間を忘れて無我夢中になる瞬間を体験する。時間を突破する・時間を超越することから、時間への正しい入り口をつかむことができます。さらに、時間との正しい関係の持ち方を獲得することで、生きることへの正しい態度を学ぶ入り口が開かれるのです。夢中体験を通して時間を超えることを体得していくことによって、子どもは正に子どもらしい、生き生きとした、子ども本来の生き方を獲得していくのです。
●はかなさから充実へ 人間の不幸や無常さについての感覚は、無駄な時間、空しい時間を過ごしたという感覚の中から生まれるのではないでしょうか。 無駄に過ぎ去り、成熟することのない時間体験を通して、人はむなさしを感じることとなります。 充実し、役に立ち、意味のある、豊かな楽しさに満ちた、良き時間の体験は、消えていく時間、絶えず過去のものとなっていく時間への空しさを、乗り越えることができる唯一の生きた体験であます。 生きる喜びに満ち満ちた、創造的な時間体験は、それまでに体験した様々な時間体験や場面体験を、統合・調和させ、さらに積極的、創造的に生きようとする姿勢を、子どもたちの中に作り上げていく原動力となるのです。
(5)コミットメントについて 「Commitment」(ランダムハウス英和辞典より)
1. 委託(委任)すること、付託行為
2. 委託(委任)されている状態、付託状態
3.略
4. 拘留、収監、拘禁、投獄
5. 精神科施設への収容
6. 精神科施設への収容命令
7. 拘禁状
8. 犯行
9. 公約(誓約)すること、言質を与えること
10. 公約、誓約、約束、義務、責務
11. 関わりあうこと、参加、連座
12. 売買契約、有価証券の売買 1~12の意味のうち、文脈によってそれぞれ固有の意味が生まれてくるが、時にはこれら12の意味内容を越えて、さらに深い意味を「響かす」こともあります。 例えば、1.「委ねる」ということは「神に魂を委ねる」の意味に使われ、さらに神や使命への「献身」という意味ももっています。つまり、1と同時に2~12の意味を「内包」しているのであり、10の神との約束や契約、11の神との関わり・集中の意味合い、4.5.6.の意味さえも含みながら、「人間の決断的行為の意味」という響きをもっているのです。 以上のような背景をもって、COMMITMENT(委員・会)という言葉が成り立っています。 教育の世界において、Commitmentという語が使われるとき、1の「委ねる」の意味で「使命への献身」という意味と、2の「委託される」の意味で、親や子どもたちから「委ねられている」という意味、さらに10、11の意味も含み、教師の子どもたちへの教育的な愛と献身と責任意識に促されて、「集中し熱中する決断と態度」をあらわす語であるように思います。 教育に携わるか否かにかかわらず、人間の基本的姿勢に関わる語です。 「委ねる」と「委ねられる」という「二つの方向」が一つの語の中に意味されていることに注目すると、「委ねる」という行為のもつ両面性・両義性を示していることがわかります。「委ねることは委ねられること」であり、「献身するとは献身される」ことです。ここに響きあいながら共に生きる、「響存と共存の人間関係」が現れてきます。「愛することは愛される」ことであり、信頼と尊敬、畏敬と畏怖の関係において、相互主体性を尊重しながら成り立つ、人間存在の弁証法的真実があきらかとなるのです。 相互委託は同時に相互主体性の実現の場としての幼稚園の在り方に深く関わっています。子どもの主体性と教師の主体性と、さらに幼稚園の理事者の主体性と、父母や地域の人々の主体性との相互主体性が、保育の営みを支え、子どもの人間としての発達を豊かに実現していく場としての幼稚園づくりの根底となるのです。
(6)指導計画について
参考文献[7] <O.F.ボルノー著『時へのかかわり』時間の人間学的考察 川島書店刊>より。
●[プランとは] 「PLAN-PLANUM」:平坦な・平面図・案内図・市街地図(空間的思考特性をもつ言葉) あらかじめ決められた設計図の図面通りに建築する。空間と時間との関係における混乱を内包している言葉。 「出来上がっている図面」という閉鎖的・完結的な「空間についての考え方」が、「計画通りに実行されていく」という、「時間的な考え方」にまで普及し転用され変造されてきました。 ”ただ、現在において完全に知られているもののみが、こうしてプランニングの中に正当にはめ込まれうる”(p.107) ”そのなかで起こりうる一切のことがすでにあらかじめ、それの本質上確定しているような世界・・閉じられた世界・・閉じられた時間”(p.108)
●[計画の限界と教育における自由] ”あらかじめ・・計算し・・えない、ということが教育の最も中心的な本質に根差している・・(シュプランガー)・・計画不能性について知ることは、それゆえに教育者の自己理解にとって決定的な意味をもっている。”(p.110) ”有限な存在としての人間の本質に属しているような限界・・”(p.112)
●[限界内での計画の可能性] ”ひとたびプランニングには限界がありうるという思想をよく知ってしまえば、やがて、様々な生活領域がきわめて様々な程度においてプランニングを受け入れるものであることに気づく。”(p.113) ”立案することは、あらゆる理性的かつ責任のある生活の必然的な前提・・ただ、結果を絶対の厳密さで確定することだけが断念される・・”(p.114) ボルノーは、さらに「先慮」・・備えとしての配慮、備蓄的な計画、内面的な心構えとしての覚悟について、不確実さと共に生きること、不安定さの中で未来に対する希望と信頼に基づく危機のただ中での確かさを語る。それは、世界と時間と人間とを未来に開かれたものとしてみる視点から、私たちに開かれてくる人間的確信であります。
7. まとめ
(1)響きあう人間関係 指導する者と指導される者とは、共に生きる者として喜びや感動を分かち合い、苦しみや悲しみを共有しあう関係の中で、人間として、また「人格として出会う者たち」です。 「同一の場」ではありえない「異なる場」に立ちながらも、互いの存在の最も深いところで通底しあっている者同士です。 転移する気分、響きあう喜びを分有しながら、響存の場において生きるもの同士、それが教師と子どもであります。 人間であることに相応しく生きる、それに向かって共に学び、未来を生みだしていく場において、創造的営みの喜びを分有する者たちです。 子どもも教師も、内なる生命の躍動に揺り動かされながら、炸裂し、激動し、覚醒してくる人間的なるものへの発見と気づきを、日々体験していくような自己形成的生活をおくる者でありたいと思います。
(2)偽文化の切り売り的教育からの脱出 教え授ける式のえさやり保育や、形式的・固定的・機械的・一方的な押しつけ保育を否定して、子どもを人間として尊重する保育を確立していきたい。これまでの教育界において支配的であった、知識の切り売り的指導方法を徹底的に排除し、真の人間教育を実現していく道を明らかにしていくことが必要であります。
(3)創造的営みとしての指導 日本人は、昔から子どもを「授かりもの」といい、幼児期を「神のうち」とよぶ謙虚さをもっていたことを心に銘じたい。 最近、子どもだけでなく大人の中にも、コモンセンス(共通感覚)の欠落が目立ってきているように感じます。いわゆる立居振舞・挙措動作が不自然であったり、不器用であるというタイプの人が目立つ時代である。言葉遣いや発言のタイミングが場に相応しくない等々の点において、未成熟な、または成熟することを諦めてしまう幼児化現象が一般化しつつあると思われる。(K.ローレンツ著 『遊びと発達の心理学』参照) 誕生から子ども時代を経て大人になっていく過程において、特に幼児期において感覚諸器官への様々な感覚情報のインプットがどのようになされるかが、人間としての発達に、生涯重大な影響を及ぼすことを改めて確認したい。 子どもは身体の誕生によってこの世界の中に生まれ、そして、教育によって人間としての誕生に向かっていく存在であります。 その教育とは、基本的に自己教育であり、自己内形成者(自ら育つ力をもっている主体者としての子ども)を前提とした教育であり、また、その方法を構築していくことを第一の課題とする教育であます。 人間はそこにただ存在するだけでは、いまだ人間であることの内実を獲得しているとはいえないのであり、存在することの意味と価値を「問う存在」として、また「問い続ける存在」であるときに、人間に相応しい存在に「なる」のであります。 そのような問いに向かって、人間を開いていくのが教育の任務なのです。 そこで必要となるのが、人間の歴史的・社会的・文化的な諸価値であり、それらを伝承していく営みとしての教育です。 それら全てを教師が背後に背負って、子どもに切り売りをし、一方的に押しつけて、動物への餌やり式に与えていく「古い教育の時代」は、もはや終わったのです。 子どもをあたかも動物のように飼育し、仕込むことによって、飴とムチや賞罰を通して形式的・生物的に飼い慣らす方法、また植物を栽培し手入れをして仕立てていくような一方的な方法、さらに木工工作にも似た設計図通り、計画通りに作り上げていく職人的方法など、さらにみせかけの科学主義や合理主義に基づく、知識・技術・技能を子どもという受け皿に注入し与えていくという、非人間的な機械論的方法等々は、いずれも「人間の教育に相応しくない」ことを銘記すべきであります。 ただ一度限りの、繰り返しのきかない、かけがえのない幼児期を生きる子どもたちが、真に幼児期でなければ経験できない、幼児期にふさわしい豊かな子どもの文化を、日常の生活の内容として、できる限り確かな量と質において、保障していく保育の営みを大切にしたいのです。 幼児の発達に適応しているとは到底思えない、過重な課題を無理やりに押しつけて、「やればできる」「やらせればやれる」という、親の拍手喝采を期待するような「子ども否定」の、「子ども殺し」にも似た「非人間的な所業」を、幼児教育の世界に許してはならないのです。 保育とは創造的な営みであり、日々に新しく生みだしていくものです。 教師と子どもによる「共同の創造的営み」としての、保育の理念とその方法を確立するために、さらに一層の努力を傾けていきたい。幼稚園とは、子どもと大人の幸せづくりと自分づくりの拠点であり、大人と子どもの安らぎの場であることを銘記したい。 1987年9月